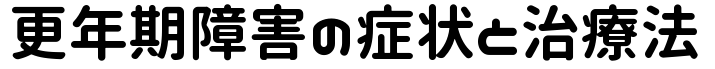エストロゲンを増やす方法とは

更年期の卵巣機能低下によるエストロゲンの減少は、 更年期障害の大きな原因となっており、 エストロゲンを増やす方法を実践することで、 これら症状を緩和することができます。
ここでは、更年期障害の症状を防ぐ、緩和する目的から、 エストロゲンを増やす方法について、いくつか紹介しています。
また、エストロゲンを減らす食べ物を避けることでも、 エストロゲンを増やすこともできます。
エストロゲンを減らす食べ物については、 エストロゲンを減らす食べ物をご参照下さい。
エストロゲンを増やす方法 一覧
エストロゲンを増やす方法 一覧
|
適正体重

そのため、痩せすぎていると、脂肪細胞が少な過ぎるため、 必要なエストロゲンを十分に産出できません。
日本人女性の平均BMIは22~23%程度ですが、 BMIが18%以下の場合、エストロゲンの分泌量だけでなく、 プロゲステロンの分泌にも影響し、無月経、若年性更年期障害、不妊、早期閉経を引き起こします。
この痩せすぎている体重を健康で適正な体重に戻してあげると、 エストロゲンの産出量を増やすことができます。
痩せすぎ体重による影響、若年性更年期障害については、 若年性更年期障害の原因と治療をご参照下さい。
ストレスを避ける

原因は、 ストレスが多くなると副腎においてコルチゾール(ストレス応答ホルモン)の分泌量を増やしますが、 これは、コルチゾールの前駆体(元となる物質)であるプレグネノロンの減少を意味し、 このプレグネノロンを利用して作られる他のホルモンであるエストロゲンやプロゲステロンの減少を意味します。
また、エストロゲン、プロゲステロンとも主要臓器である卵巣、黄体以外に副腎で産出されますが、 ストレスをかけ過ぎると、副腎が疲労しその機能が低下してしまうため、 エストロゲンやプロゲステロンの産出量が低下してしまいます。
特に更年期には、女性のうつ病発病率が2倍以上になりますが、 これはエストロゲンの低下も一要因であり、エストロゲンのレベルが低い場合、 同じ事柄でも、より多くのストレスを感じることが分かっています。
節酒を心がける

1988年に発行された薬理学的治験のジャーナルによると、 3週間毎日3杯、アルコールを飲むことにより、 月経異常、排卵欠如など、 エストロゲンの分泌を促す卵巣に異常が見られる、と発表しています。
一方、更年期や閉経後の女性においては、 卵巣でのエストロゲン分泌量が比較的低いことと、 アルコールが男性ホルモン(テストステロン)からエストロゲンへの変換を促すことから、 飲酒によってエストロゲンが増え、閉経年齢が延びるのも事実です。
ただし、アルコールの飲み過ぎは、アルコール性肝疾患やアルコール依存症など、 多くの病気を誘発することから、 厚生労働省では、一日1杯(ビール中1本、お酒1合、酎ハイ350ml程度)を適量としています。
特に閉経前の女性においては、 月経異常のほか、自然流産の増加をもたらすため、適度な飲酒、節酒が重要になります。
コーヒー

これは、 エストロゲンの代謝に使われるCPY1A2系酵素が、 カフェインの解毒に利用されるため、 エストロゲンが体内に長くとどまるためでは、と推測されています。
ただし、269名の女性を対象にした研究では、 アジア人や黒人ではエストロゲンレベルが上昇したものの、 白人においては、エストロゲンレベルが低下したため、まだコーヒーとエストロゲンの増加については、 明確な結論は出ていません。
牛乳
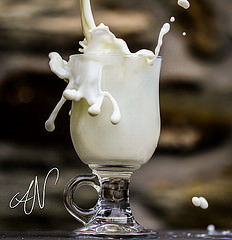
この牛乳には、女性ホルモンエストロゲンがかなり含まれており、 特に妊娠後期の牛から絞った牛乳には、妊娠していない牛の牛乳よりも、 エストロゲンが33倍も多く含まれています。
また、牛乳以外にも、バターやチーズなどの乳製品にも、エストロゲンが多く含まれています。
山梨大学の研究によると、 7名の男性、5名の女性、6名の思春期の子供が、 600ml(女性は500ml)の牛乳を摂取したところ、 血清エストロン(E1)、エストラジオール(E2)、エストリオール(E3)、 及びプレグナンジオール(プロゲステロンの代謝物)の尿中濃度が、 全ての大人と子供で増加しました。
ただし、過剰なエストロゲンへの暴露により、 前立腺がんなど、死亡リスクも増えるため、注意が必要です。
植物性エストロゲン

日本では植物性エストロゲンと言えば、お豆腐や納豆に代表される大豆イソフラボンですが、 その他にもゴマに含まれるリグナンやなど、様々な種類の植物性エストロゲンが存在します。
更年期障害の植物性エストロゲンの効果については、 更年期障害とイソフラボンなどの効果を、 また、大豆イソフラボンを多く含む食べ物については、大豆イソフラボンを多く含む食べ物をご参照下さい。
ホルモン補充療法

特にほてりや発汗などの血管運動神経症状には、 ホルモン補充療法は非常に効果が高くなっています。
一方、ホルモン補充療法には、いくつかのリスクも存在します。
ホルモン補充療法については、 更年期のホルモン補充療法の効果と種類をご参照下さい。 また、ホルモン補充療法のリスクについては、ホルモン補充療法のリスクをご参照下さい。
外因性内分泌かく乱化学物質

一例を挙げると、 化粧品や芳香剤に使われるフタル酸エステル、 シャンプーや保湿液、石鹸、クリームなどに使われるパラペン、 缶詰などから溶け出すビスフェノールAなど、は外因性内分泌かく乱物質と呼ばれ、 エストロゲンと似た生理作用をすることで、体内エストロゲンの濃度を低下させます。
外因性内分泌かく乱物質については、 ホルモンバランスの乱れをご参照下さい。
| エストロゲンを増やす方法 先頭へ |
| 関連ページ |
| メニュー・目次一覧へ |